Profile
このページは研究室配属前の学生向けの内容となっています.
それ以外の方でもご興味をお持ちの方はどなたでもご覧下さい.
どんな研究室
1996年,横山光雄先生(本学名誉教授)が通信総合研究所(現 NICT)から着任され,
移動通信方式の研究が始まりました.
これが本研究室活動開始の実質的な元年となりますが,その起源は開学時までさかのぼります.
秋丸春夫先生(本学名誉教授,故人)が主宰した「情報交換研究室」がそれです.
通信ネットワーク(有線系)分野の発展に大きな足跡を残されました.
1997年には上原秀幸先生も着任され,無線ネットワークの研究も始まりました.
以後,横山先生が退官されるまでの10年間,開学以来の伝統をもつ情報交換研究室を引き継ぎ,
有線系から無線系へ研究の軸を移しつつも,“通信”技術の発展に貢献し,
多くの卒業生を社会へ送り出してきました.
2007年,大平孝先生がATRから着任され,研究室の名称は「無線ネットワーク研究室」と変わりました.
2010年,大学再編に伴い,大平先生が主宰する「波動工学研究室」と
上原先生が主宰する「ワイヤレス通信研究室」が誕生しました.
また,研究室の所属系が,情報工学系から電気・電子情報工学系に変わりました.
2013年,宮路祐一助教(上原研出身)が着任し,9年間のご指導の後,2022年に愛知工業大学へ異動されました.
そして2023年,小松和暉助教(上原研出身)が着任し今日に至っています.
ワイヤレス通信研究室
ワイヤレス通信研究室は,上原秀幸教授,小松和暉助教,博士前期10名,学部5名で構成されています.
研究テーマについては, 研究紹介のページをご覧下さい.
研究姿勢
大学院博士後期課程
修士レベルにおける学問的な問題解決能力が十分で,
研究を自立して推進できると判断された者のみが進学できるというポジションにあります.
博士前期課程でかなりの成果が必要となり,博士後期課程への道はそう簡単ではないようです.
みなさんも自分のやっている分野を究めたい,その道のエキスパートになりたいっていう願望はありますよね?
大学院博士前期課程
自ら学問研究推進能力を身につけ,先生の指示待ちをせず,自発的・積極的な行動が望まれます.
2年生
前期末までに修士論文の大方の見通しをたて論文投稿の準備を進めましょう.1月中旬に修士論文の予備審査,その1ヶ月後に本審査があります.
1年生
修士研究のテーマを決め,自発的に研究を進めていきます.研究室の幹事学年であり講義も忙しいので,しっかりと計画を立て良い準備をしましょう.
期末ごとに研究室内で修士論文中間報告会があります.
学外での発表も活発的に行います.
学部4年生
先生や先輩の指導を受けながら,早く一人立ちするための研究のノウハウを習得します.
前期1は研究に必要な基礎力を定着させるための勉強をします.
その後研究テーマを定め卒業研究をすすめます.12月に発表会があります.卒研発表後は実務訓練を行います.
ゼミ
担当の学生は,定期的に研究の進捗状況を報告します.
何度もメンバーの前で発表をしていたら,嫌でもプレゼンテーション能力は向上することでしょう.
人に研究を理解してもらうためにどういうふうに説明したら良いのかを勉強できます.
互いが積極的に意見交換を行うことによって,研究の視野を広げます.
例えテーマが違っても,「人に自分の研究を知ってもらう」,
「自分が人の研究を知る」といった多くの収穫を得ることができるでしょう.
また,良い発表に質問をしないのは失礼です.
ゼミでは,学年に関係なく積極的に質問することが望まれています.
「用意されていない突然の質問に対して,相手が納得できるような回答ができる」,
若者達はそんな柔軟性を知らず知らずのうちに身につけていくのでしょう.
他には,論文精読を行っています. 研究の位置づけや最新の動向を確認します.
ここでも活発なディスカッションが行われ,良い刺激になります.
イベント
4月の新歓から始まり,3月の追い出しコンパまで年間を通じて多くのイベントがあります.
これらは情報通信システム分野共同で企画・運営しています.
大きな報告会の後には打ち上げ,その他ボウリング大会などさまざまなイベントが開催されます.
イベントの企画,実施は全て学生が行っています(イベント企画は随時募集中です!).
これまでに行われたイベント(ほんの一部)を紹介します.
B4研究室紹介

球技大会

研究室旅行

駅伝大会

田村研合同ボーリング大会

ゼミの様子
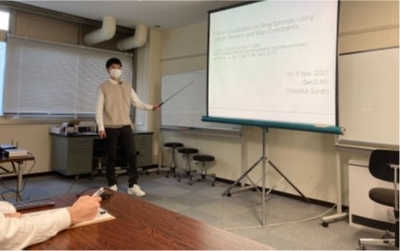
環境
実験装置
情報収集をはじめ,報告書作成,シミュレーションなど,計算機を使わない日はないでしょう.研究室の計算機は,個人で使用するマシンと,計算専用マシンとがあります.
また,各種シミュレータや計測器,プリンタなどの周辺機器, プレゼンテーション用ノートPCなども揃っています.
備品の管理は,学生が主体となって行っています.
文献
研究分野に関する論文誌や雑誌などの資料は,棚に整理され, いつでも利用できる状態にあります.これら資料は,最新の動向を調査するため,頻繁に活用されています.
談話室
メンバーの憩いの場です.フローリング風の床,ソファ,テーブル,大型プラズマテレビ,冷蔵庫,電子レンジ...,ここで暮らせます.研究室業務(M1の仕事)
M1の各メンバーは何らかの役職を持ち,研究室の業務にかかわり,運営に協力しています.
いくつか例を挙げると...
- 総務
- 研究室の総括
- 会計
- 研究室の財布のヒモを握れる
- 計算機管理
- 研究室にある計算機の管理,メンテナンスを行う
これら仕事は,自発的に行うというシステムです.
自分がやりたい仕事があったら,どんどん言ってきてください.
進路
学部卒業後の進路
学部卒業後の進路としては,本学大学院への進学,他大学大学院への進学,就職が考えられます本研究室では,ほとんどの学生が大学院博士前期課程へ進学します.
2022年度を例に挙げると,6名全員が本学への進学を希望しました.
進学希望の6名は全員推薦入試を受け,見事全員合格しました.
博士前期課程修了後の進路
博士前期課程修了後の進路としては,博士後期課程への進学,就職が考えられます.2022年度は4名の修了生が希望した就職先へと就職しました.